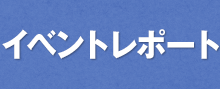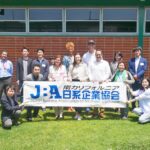2025/4/1
企画マーケティング部会 特別経済セミナー 「米国経済・金融市場の見通し ~トランプ2.0の始動~」 報告
去る2月5日(水)、企画マーケティング部会によるJBA特別経済セミナー「米国経済・金融市場の見通し ~トランプ2.0の始動~」をオンラインで開催した。
 [講師プロフィール]
[講師プロフィール]
坂本篤秀さん
三井住友銀行 市場営業統括部(ニューヨーク) シニアエコノミスト
2010年三井住友銀行に入行。12年より同行エコノミストとして米国の経済・政治・金融市場分析を担当。
株価・個人消費とも堅調が予想される今年のアメリカ経済
第二次トランプ政権が米国経済、金融市場にどういった影響を及ぼすかという非常に注目度の高いトピックでの開催となった本特別経済セミナー。坂本さんは冒頭で、「関税関連を含め、トランプ大統領が半ば朝令暮改のような形で大きく動いています。そうした中で、アメリカ経済・金融市場の今後に関して注目すべき点についてお話しします」と述べ、①格差を内包しつつ堅調な米国経済、②FRBは利上げに慎重姿勢、③トランプ2.0の始動、④米国経済は黄金時代を迎え得るか、という4つのポイントで話を進めていくとした。
坂本さんは初めに今年のアメリカの金利と為替の変動に関して、三井住友銀行としては、年内に0.25%の利下げが2回行われ、またドル円は今年末時点で1ドル=145円程度になると予測しているとした上で、「個人的な見通しとしては、2回の利下げは難しく、0~1回に留まるのではないかと考えています」と述べた。そして、世界各国と比較してもアメリカ経済一強の状況であり、個人消費も堅調で地力が依然として強いと、アメリカの経済の底堅さを強調した。
続いて、アメリカ経済の問題として格差を挙げ、「所得階層別に消費者センチメント(消費者が現在の経済状況や将来の景気についてどのように感じているかを示す指標)を見ると、高所得層のセンチメントは回復している一方、低所得層は回復していません。所得上位20%が消費全体の40%を占め、所得下位20%は消費全体の8%に留まるため、所得下位層のセンチメントが悪くても個人消費額全体に与える影響は少なく、マクロに与える影響力の格差が広がっている点には注意が必要です」と述べ、より影響力の強い高所得者層の購買力の原資である株価に話題は移った。
「S&P 500のPER(Price Earnings Ratio=株価収益率)を見ても、アメリカの株価は割高、そして10年金利(満期が10年の国債の利回り)も依然高いことから、アメリカの株価は今年難しい局面を迎えることは間違いないでしょう。では大幅調整、大きな下落があるかというと、私は懐疑的です。トランプ政権、FRBとも株価の大幅下落、金融システムの動揺を避けたいと考えているためです。ゆえに、今年の経済は、株価の大崩れは免れ、高所得層の購買力はある程度維持され、個人消費は維持され、経済成長もある程度底堅く保たれるだろうと見ています」と予測した。
 市場混乱を避けたいトランプ政権・FRB両者の意向に支えられ、大きな株価下落の可能性は低いとの予測。
市場混乱を避けたいトランプ政権・FRB両者の意向に支えられ、大きな株価下落の可能性は低いとの予測。続いてトピックは企業サイドからの見方に移る。アメリカで8割を占めるサービス業のセンチメントは堅調、2割を占める製造業はやや不調であるとし、家計と同様、影響力の大きい層は好調、小さい層は不調で、全員がハッピーではないが総論OKという状況だとまとめた。そして、「総論OKと言いましたが、その中での問題はインフレが続くという点です。サービスの物価はピークアウトしているものの、依然底堅い状況が続いています。サービスの原価である人件費も、ピークアウトしているものの底堅く、これがサービス物価の高止まりにつながっていると思われます。
また、少し話が反れますが、トランプ2.0においてアメリカの企業・家計はどうなっているのかという点にも触れます。共和党支持者が多いと言われる中小企業、共和党支持者の家計のセンチメントを見ると、この数カ月で明らかに数値が改善しています。これらはセンチメントに過ぎないのですが、その『センチメント=気分』が支出、企業の場合は設備投資を増やす、つまりセンチメントが自己実現的に需要を生み出すこともあり、今後その動きがあるかに注視しています」とした。
そしてセミナー前半の最後のトピックとしてFRBの金利政策に触れ、「景気は堅調、インフレが続き、トランプ政権下では移民の抑制や関税の増税といったインフレ再反発(一度落ち着いたインフレが再び加速すること)のリスクのある政策が打ち出されようとしています。その中でFRBは利下げをできるかというと、慎重にならざるを得ないと思っています。金融市場も今年2回の利下げを織り込んでいますが、本当に2回利下げできるのか、私は懐疑的です」とまとめた。
トランプ2.0のカギを握る四つのプレーヤーと、関税・移民政策がアメリカ経済に与える影響とは
続いてトランプ2.0に話題は移り、坂本さんは①各政策を巡るパワーゲームは複雑化、②各政策による経済影響、③米国経済は黄金時代を迎えられるか、の3点を挙げ、話を展開した。
まず、「①各政策を巡るパワーゲームは複雑化」におけるプレーヤーとして、「ナショナリスト」「経済成長推進派」「財政保守派議員」「ロシアと中国」の四者を挙げ、順にその影響を解説した。「ナショナリストは経済合理性よりアメリカファーストが重要、関税をかければ自分たちに製造業が戻ってくる、といったストーリーを信じる価値観ベースの人たちです。この反対にいるのが経済成長推進派と呼ばれる、経済を比較的理解している層で、関税は経済に悪影響と考え、減税や規制緩和を推進したい人たちです。この両者が政権内で勢力争いをしています。
もう一つの重要なプレーヤーがフリーダム・コーカスと呼ばれる財政保守派議員。財政赤字、歳入減を許せない人たちで、減税を進めたいトランプ大統領と彼らの間で交渉が難航するのではないかと思っています。最後のプレーヤーがロシアと中国。就任後の動きを見るに、ロシア・ウクライナ戦争の停戦交渉は難航していると見られ、停戦が難しくなると得をするのは、ロシアに対して影響力のある中国です」とし、政権の中でこの四つのプレーヤーの思惑が揺れ動いていること、またトランプ大統領自身も自由ではなく、これらのプレーヤーの関連しない、実行しやすい政策から進めていると現状を分析した。
 政策一つ一つを見るのも大切だが、その政策を巡ってどういったパワーゲームが起きているかを読み解くことがより大切、と語った坂本さん。
政策一つ一つを見るのも大切だが、その政策を巡ってどういったパワーゲームが起きているかを読み解くことがより大切、と語った坂本さん。
次に、「②各政策による経済影響」に話は移る。「トランプ大統領が現在示している減税・関税の課税を全て実施した場合の影響を計算すると、GDPを減税で2.4%押し上げ、関税で1.7%押し下げ、トータルではプラスになる見通しです。しかしその影響は均一ではなく、関税は消費税のように消費者全員が同じ影響を受ける一方、減税は高所得者層がより大きな恩恵を受けます。今回の大統領選挙では低所得者層がトランプ大統領に鞍替えしたと言われていますが、減税は彼らにデメリットのある政策ですから、2026年の中間選挙に影響を及ぼす可能性があります」と述べた。そして関税の各国への影響については、25%が課されたカナダ、メキシコへの影響は非常に大きいが、これは交渉に利用するための一時的なものと考えられる点、10%が課された中国に関しては交渉が難航する可能性を指摘した。
続いてトピックは、関税よりも重要なポイントという移民政策に移った。18~19年の第一次トランプ政権下で行われた「移民不寛容政策」により、移民労働力の不足により賃金が上昇した結果、アメリカ生まれの労働力人口が増加したと指摘し、「今回、これと同じように、労働コストの上昇が起こる可能性があり、注意が必要です」と、移民抑制が今後関税・減税政策以上にアメリカの経済と労働市場に影響を与える可能性があると提起した。
さらにアメリカの金利が昨年の大統領選挙以降上昇していることに触れ、「金利の中でもタームプレミアム(≒財政リスクプレミアム)が上昇しているのですが、これはトランプ政権下で政府債務が悪化すると見られているためです。FRBの動向に加えて、こうした財政リスクプレミアムも考慮され、この面から見ても、アメリカの金利は下がりにくい状況です」と、各政策の経済影響についてまとめた。
アメリカが再び黄金時代を迎えるかは、AIの普及がカギ
トピックは「③米国経済は黄金時代を迎えられるか」に移った。アメリカ経済の観点から見ると、IT革命が起き、『Windows 95』が発表され、IT関連の規制緩和が起き、生産性が一気に上昇した1990年代が黄金時代と言えるとし、「足元を見ると、生産性が若干上昇する気配があります。これは生成型AIの影響で、今は生成型AIの黎明期を迎えていると指摘できます。トランプ大統領もAIをより低コストで普及させようとしています。
ここで、現在話題の『DeepSeek』(中国企業が開発したAI言語モデル)についてですが、ポイントはオープンソースが作られたという点です。今まで高コストだったAIを低コストで利用できるようになり、今後は同様にアメリカ企業も模倣できる可能性がある、そうなればこのイノベーションが黎明期から普及期に移行するきっかけとなり、90年代後半のような黄金時代を迎えるかもしれません」と、アメリカ経済とAIの今後の展望をまとめるとともに、今後のリスクとして①インフレの再加速、②株価の調整局面入り、③トランプ大統領の領土的野心の拡大、の3点を挙げ、これらを注視することを促し、セミナーを締めくくった。
 AIの普及により労働生産性が継続的に上昇することがあれば、アメリカ経済が黄金時代を迎える可能性も。
AIの普及により労働生産性が継続的に上昇することがあれば、アメリカ経済が黄金時代を迎える可能性も。