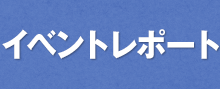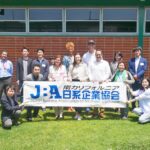2025/4/1
教育文化部会 教育ウェビナー「デジタル時代の漢字力と漢字教育を考える パート2 家庭でできるサポート編」報告
去る2月23日(日)、教育文化部会主催の教育ウェビナー「デジタル時代の漢字力と漢字教育を考える パート2 家庭でできるサポート編」をオンラインで開催した。
 [講師プロフィール]
[講師プロフィール]
ダグラス昌子さん
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 名誉教授/アジア・アジアンアメリカン研究学部日本語科
専門研究分野はカリキュラムデザインとインストラクション、継承日本語の発達、リテラシー(漢字力、読みの力)の発達など。バイリンガル・マルチリンガル子どもネット理事、全米コミュニティーベース継承語学校連盟理事、全米日本語教師連盟継承語部会会長。
「書ける」から「使える」へ。デジタル時代の漢字力
日本国外におけるデジタル時代の漢字力、漢字教育という、多くの在米の保護者にとって関心の高いテーマで行われた本セミナーは、昨年に続いてのパート2。ダグラス教授は冒頭で、事前の参加者アンケートから、保護者が小学生の時には、ドリルなどに繰り返し書いて覚えたという声が多い、そして現在補習校などに通う子どもの宿題も、ワークブックやプリントを使って練習するなど、保護者の世代と比較して大きな変化がないことを指摘した。
次に昨年の振り返りとして、デジタル時代において、求められる漢字力と学校での漢字教育に大きなギャップが生まれていると述べた。「手書き時代において漢字は読めて、書けることが必要でした。しかしITの時代には、漢字は読めて、正しく使える、正しく『選べる』ことが必要になっています。日本の文化庁文化部国語科の調査によれば、手書きをしなくなった分、漢字を正確に書く力が衰えていると感じている人が増えているというデータが出ています。
一方、例えばアイサツという言葉をひらがなで書くか漢字で書くかを問うと、デジタルデバイスを利用する場合は漢字を選ぶ人が増えています。手書きは難しくても、正しい漢字を、自信を持って選べる人が増えているというデータが出ているわけです。デジタル時代の漢字力は、漢字の語彙の意味を知っていること、そして漢字の構成の部分的な知識があることが重要で、その知識があれば、正しい漢字を選べるのです」と述べ、デジタルデバイスを活用することで、伝えたい内容を考え書くことに集中できるという利点を指摘した。
次に、テーマは漢字の学び方、漢字力の発達に移る。新しい語彙を学ぶと、まず見て分かる受け身的な語彙「受容語彙」となり、その次の段階として、書いたり話したり自分から発信できる「表出語彙」となるとした。そして、「さらにこの上の段階として、手で書ける、つまり完全に音と意味と字形を覚えているという段階があるのですが、デジタル時代にこのレベルが必要かは大きな疑問です。昔の学校での漢字教育を振り返ると、手書きができるようになることに多くのエネルギーが費やされていました。ですがデジタル時代の漢字力とは、字の知識ではなく語彙の力であり、使い方が分かることです」と、現在求められる漢字力についてまとめた。
 デジタル時代の漢字力とは、正しい漢字を選び使える「語彙力」。
デジタル時代の漢字力とは、正しい漢字を選び使える「語彙力」。求められる漢字力と漢字教育の現状の大きなギャップ
次に子どもたちの漢字の学習法に話題は移り、「学校での漢字教育は、冒頭に紹介した、保護者の皆さんが小学生だった頃の漢字教育とあまり変わっていません。ドリル学習、とにかく書いて覚えるという学習法は、補習校に留まらず日本でも同様に行われていて、指導者が漢字の読み方・書き方を示し、画数と筆順を覚えて、なぞり書きをする、そらで書くといった教育が依然行われています。宿題も、漢字帳・ドリル・ワークブックを使い繰り返し書かせるという学校が多く、それ以外の方法を考えるのが非常に難しい状態です。このように日本の漢字教育が変わらない理由は、教える立場である先生が、自身が子どものころに習った方法を変えられないからだと考えられます。
文部科学省は、例えばある漢字が複数の筆順を持つこと(『必』など)、複数の画数を持つこと(『衣』など)を受容しているのですが、指導者は依然として自分が小学校で習っていた基準でマルバツを付けている。このような矛盾の中、子どもたちは一生懸命に勉強しています。デジタル時代に必要な漢字力とは何かが討論されないまま、従来の漢字教育がされている、これは大きな問題だと思います」と、指導者の現状に問題提起。一方子どもたちは、漢字の中にほかの漢字の形を見つける、トピックと結び付ける、アルファベットの形と関連させて覚えるなど、自分なりにいろいろな方法で覚えようとしており、こういった方法は認知心理学という分野から見ても非常に効果的な学習法であると指摘した。
次に止め・はねに関する指導についても触れ、「文化庁文化部国語科指針によれば、『漢字の骨組みに関わらない場合には誤りとしない』つまり、はねの有無は問わない、また例えば『保』の右下部分は『木』でも『ホ』でもよいという見解です。ですが学校の漢字テストだと誤りにされる場合がある。指導者には、生徒・児童が書いた漢字を評価する場合には柔軟に評価することが求められます。特に漢字を勉強し始めの低学年の生徒には、認知的に負荷がかかり過ぎないようにするべきです」と、指導者の変革を訴えた。このトピックの最後として手書きの有効性について触れ、「ではデジタル時代に手書きは必要ないのかというと、そうではなく、漢字の組み立てを理解するには有効です。漢字は『積み木』のように組み合わせでできていること、例えば『休』はにんべんと『木』の組み合わせだと単位ごとに意識することができるようになります」とまとめた。
 現実に即して漢字教育も変化すべきと指摘したダグラスさん。
現実に即して漢字教育も変化すべきと指摘したダグラスさん。家庭でできるサポート ~学習段階に応じた有効な漢字学習の方法とは~
セミナー後半のテーマ、「家庭でできるサポート」に入るとまず、アメリカで育つ日本人・日系人の子どもは英語・日本語両方を同時に勉強していく環境であることについて触れ、「彼らには、左から右に流れる英語と、上下・左右・内外に組み合わさる漢字の組み立ての違いを教えてあげないといけません。知っているパーツに分けてみるという練習、これとこれを足したらどんな字になるでしょう、とパズルのようにすると子どもたちも喜んで取り組みます。漢字学習に苦手意識を持つお子さんには、小さな、簡単なタスクに分けることで、小さな達成感を多く与えることが必要ではないかと思います」と述べた。そして、学習初期・中期・後期に分けて、それぞれ下記のような学習方法を勧めた。
インデックスカードを使って漢字の分解練習をする、漢字の足し算をする、イラストを使って象形文字は物の形から漢字に発展した経緯を見せる、漢字をイラストと結び付ける(連想法)、手紙やメッセージを書く時に漢字のところを絵で描く、文の中で漢字で書くべきだと思う(書ける)単語にマルを付ける、などの活動で、漢字の表意感覚を発達させる。
熟語の中のそれぞれの漢字の読み方を明確にし、音で聞いた語の漢字の区切りがどこかを選ぶ練習。同じ漢字でも、文脈によって読み方が変わることを理解しているかを確認する練習、読みと漢字を結び付ける練習など。
この段階になると、学習者が自分にあった学習方法を見つけ、自律して学習し続けることが大切になる。例えば「暑い」と「寒い」のように対になっているものを自分で整理して集める、「不」「無」「非」といったネガティブな意味を表す接頭辞を一つのグループにして覚える、同じ部首や部分を持つ漢字は半数以上同じ音を持つことを覚える、同じ読みを持つ複数の部首を覚えるなど。
このように、学習後期にはグループ化・抽象化が重要になるとした。
最後に、「一方、例えば『皮肉』の『皮』と『肉』という組み合わせのように、漢字の元の意味とは全く違う意味になる漢字もあるので、文脈から情報を理解する指導・サポートも必要になります」と指摘。例えば、「月食」という単語を例に、「月食とは、あまりアメリカでは耳にしないトピックで、理科で勉強しない限り出てこない言葉かもしれません。こういった単語の場合、月食はLunar eclipseだよと教えてしまうのではなく、子どもがテキストを読み、文脈に即して意味を推測し理解するという練習が重要です。子どもが自分自身で意味を表しているところを探すことで、リーディングの能力が発達していくのです」とし、漢字学習の発達段階ごとに有効な学習方法が異なる点をまとめ、セミナーは幕を閉じた。
 漢字学習初期・中期・後期それぞれに適した学習方法が紹介された。
漢字学習初期・中期・後期それぞれに適した学習方法が紹介された。