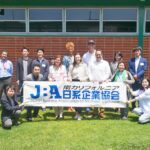2018/10/11
企画マーケティング部会 第213回 JBAビジネスセミナー報告「米国訴訟裁判・仲裁裁定 ~プロセスの理解と勝訴への戦略~仮定訴訟ケーススタディー」
去る10月11日、第213回JBAビジネスセミナーを開催した。今回の講師は北川&イベート法律事務所の北川リサ美智子弁護士。日米での訴訟のあり方の違い、アメリカでの訴訟において日系企業が注意すべき点などについて、自身の経験を踏まえて解説した。

[講 師]
北川リサ美智子さん
北川&イベート法律事務所弁護士。カリフォルニア州、テキサス州、ジョージア州、ニューヨーク州の弁護士資格を所持。ビジネス法を専門とする。日本では東京大学、京都大学に在籍。日米両国の大学で教育を受けた経験を生かし、数多くの日系企業をクライアントとしている。

「このセミナーでは、訴訟のプロセス全体についてお話しします」と始めた、講師の北川リサ美智子弁護士。訴訟と仲裁裁定における日米の違いを明らかにしながら、アメリカでの訴訟で日系企業が注意すべき点について解説した。
はじめに、アメリカの法律は「連邦法」と「州法」に分けられると説明。連邦法が適用されるのは憲法に関わる案件、原告と被告が異なる州にいる場合、訴訟金額が大きい場合などに限られる。一方、「州法」については、アメリカでは州の権限が強く、州によって法も考え方も違うというのが特徴である点、連邦訴訟は州の訴訟より進行がはるかに早いことも指摘した。
アメリカの訴訟の特徴として、「訴訟の進行は非常に早いです。日系企業は、日本本社との連絡や日本本社での稟議等が必要となりますが、このスピード感には注意が必要です。また、日本企業は訴訟における地域文化や心構えをもっと認識すべきです」と北川さんはアドバイスした。
「訴答」から「裁判後」まで5段階で進められる訴訟
まず、訴訟のプロセスについて解説。「訴答(Pleadings)」「情報開示(Discovery)」「申請(Motions)」「裁判/仲裁裁定(Trial/Arbitration)」「裁判後(Post Trial)」の5段階に分けられるとした。
第1段階の「訴答」は、訴状が提出され、訴えられた側が答弁や返答を行うという段階だ。アメリカでのユニークな制度として、「Does 1 through 100」を紹介。もし最初に訴えた相手の他に、この訴えに関連する第三者がいた場合、この第三者も同じ訴訟の被告として加えることができる、という制度だ。
また、管轄権についても言及。「一般的に、日本の親会社とアメリカの子会社は別の株式会社の形を取っているため、親会社には直接の管轄権がないことを認識しておいてください。ただし、過去に消費者に怪我をさせてしまった『製品責任』に関わる訴訟では、米国子会社に対する令状等は日本の親会社にも効力があると裁決された例もあります」と述べた。
第2段階の「情報開示」は、質問書の作成をしたり、書類提出のリクエストをしたり、「証言録取(Deposition)」を実施したり、時によっては、専門家の証人から証言を取るという段階。5つのプロセスの中で最も時間と費用がかかる。特に費用に関しては全体の7割程度がここにかかるとのことだ。
「証言録取」は、従来は直接会って行われてきたが、今ではインターネットのスカイプ等による証言録取が可能。技術の進歩により、利便性の向上と費用の節約が実現すると話した。また、映像を録画される録取において日本人が気を付けるべき点を指摘。「日本人は、あいづちを打つ時に頷く仕草をするのが一般的ですが、これはアメリカでは『イエス』や『賛成』を意味します。言葉で認めなくても、仕草だけで『イエス』と受け取られてしまう可能性があるので、十分注意する必要があります」とアドバイスした。
他に、「情報開示」で重要なポイントとして、専門家の証人を挙げた北川さん。良い証人の証言を得られると、訴訟をうまく進められる。「専門家と言っても、誰が良い証人なのかは、レジュメだけでは分かりません。インタビューが必要です。経験や能力はもちろん、話し方やコミュニケーションの取り方も重要です。大きな声で堂々と話せることも印象として大きいのです」とした。
第3段階は「申請」。実際に裁判となる前に、争点の審判、略式判決、証拠に関する申請といった手続きができる。実際には、紛争が裁判まで至ることはまれで、連邦民事事件で見ると、実に95%は裁判に至らずに解決しているとのことだ。
第4段階として実際の「裁判」「仲裁」が行われ、第5段階の「裁判後」では、裁判・仲裁の結果から次の方策を検討する、というのが訴訟の一般的なプロセスだ。
「裁判」と「ADR」 どちらで訴訟を進めるべきか
次に、訴訟は大きく「裁判」と「ADR(裁判外紛争解決、Alternative Dispute Resolution)」に分けられるとし、その特徴と企業が取るべき方策について解説した。
まず「裁判」は、上告が可能で時間がかかるため、費用も高額になるのが一般的だ。また、陪審員制度について、「刑法に関する事項であれば陪審員制度は有効ですが、ビジネスの訴訟では怖いと思います。誰が陪審員を務めるか分からない、コントロールできない点がリスクです」と意見を述べた。
裁判は公共の裁判所で行われ、多くの情報が公表される点も挙げた。裁判になると、インターネット、テレビなどで、個人の名前を含む多くの情報が公に晒されることになり、企業イメージに影響を与える可能性は大きい。さらにスケジュール面でも、裁判官の都合に合わせざるを得ないため、時間のかかる民事訴訟に日本本社から重役が赴くことの難しさを指摘した。
一方「ADR」は、「仲裁」「調停」などの解決法で、25年ほど前から一般的になってきた。ADRのメリットとしては、仲裁者・調停者を当事者で選ぶことができる点、費用を抑えられる点、スケジュールや場所をある程度自由に決められる点、情報が外に出にくく秘密を守りやすい点などを挙げた。その上で「調停」と「仲裁」について詳細に解説した。
「調停」は、比較的カジュアルに進められる。原告と被告がそれぞれ別の部屋に分かれ、調停者が両者の意見を順番に聞いていく。調停で、和解に達すれば、和解契約書または基本定款を作成。一方、調停で和解に達しなければ、訴訟や仲裁裁定を続けることになる。
次に「仲裁」だが、ADRの中でも、ある程度「仲裁者」の決定に強制力があるのが特徴だ。仲裁機関を利用することが多く、AAA(American Arbitration Association)、JAMS、Judicate Westのような仲裁機関がある。仲裁者は多くの場合、退職した裁判官や弁護士が務める。仲裁の審問は仲裁者の事務所やホテルの会議室などで行われる。「裁判では当然、裁判官を選べませんが、仲裁であれば仲裁者を選ぶことができます。これは大きなメリットです」と強調した。
また北川さんは、企業に対しては、各従業員とあらかじめ「仲裁同意書(Mutual Arbitration Agreement(MAA)」を結んでおくことを勧める。これを結び、署名をもらっておくことで、何かトラブルが起こった際も、陪審員裁判で争うことなく解決することが可能になる。
早期の相談が重要 トラブルを予想した対策を!
まとめとして、日系企業へアドバイスを送った北川さん。何より、なるべく早く弁護士に相談することの重要性を説いた。「トラブルが起こってからではなく、トラブルの原因になりそうなことがあれば、早く弁護士に相談しましょう。リスク管理をしておくことも有効です」ということだ。
契約を結ぶ際にも、トラブルを未然に予想し、仲裁の裁定方法や準拠法、裁判になった場合の場所に至るまで、詳細に決めて契約をしておくことが大切だと話す。
最後に、弁護士の選び方としては、「Partner」であるか、それ以外かという点に注目すると良いとした。もし、その弁護士が「Partner」でない場合、権限や力を持ち合わせていないためだ。大型弁護士事務所で、「Counsel」「Senior Associate」と名乗っている場合、権限がなくインディペンデントコントラクターである場合がほとんどだという。
また、アメリカでは州によって弁護士資格の取得の難易度に差があり、どの州の弁護士資格を持っているかを確認することを勧めたほか、弁護士と直接コミュニケーションを取ることができるか、も重要な点であると述べた。「言語力よりも、考え方やコミュニケーション能力に目を向けるべきで、アメリカ流の考え方を持った弁護士の方が良いです」とアドバイスした。そして前述の通り、裁判や仲裁に至る訴訟は全体の5%程度であることに触れ、「裁判や仲裁の経験がある弁護士は多くありません。実際に判決や裁定が下されるまでを経験している弁護士を雇うことも重要です。経験豊富な弁護士ならば、効率的なプランを練り、勝訴へ導くことができます」とまとめた。